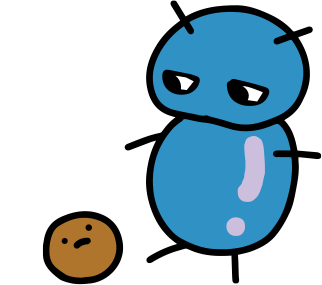
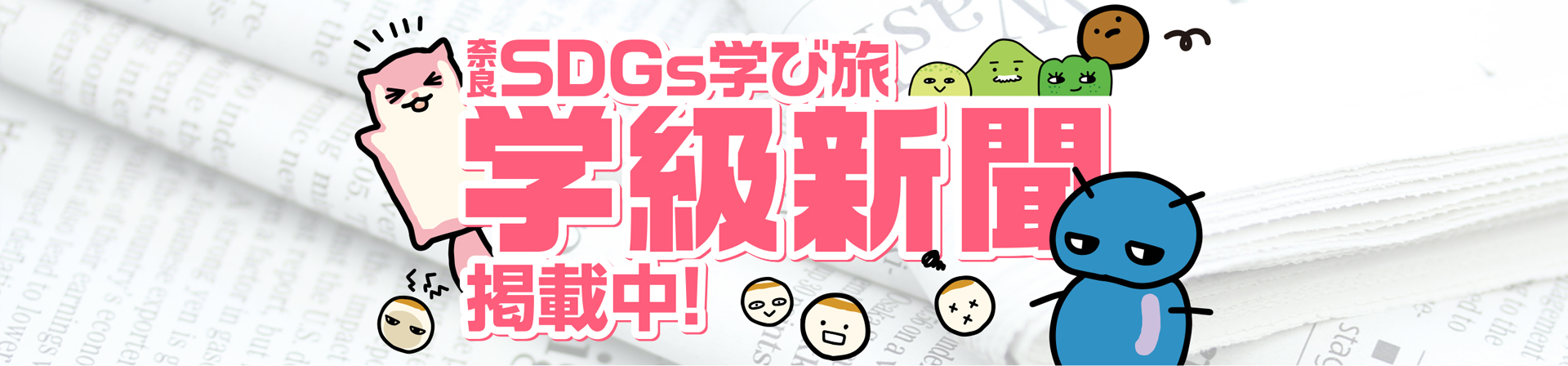
オーバーツーリズム世界自然遺産5地域会議地球市民知床財団餌付け

【第68号 2025/5/13 発行】
----------------------------------------
[1] 奈良SDGs学び旅 問合せ報告/実施報告
[2] はばたけ ルリセンチ No. 67
[3] 当社代表取締役によるコラム
[4] お知らせ
----------------------------------------
[1]奈良SDGs学び旅 問合せ報告/実施報告
●問合せ報告
・2025/11/06 神奈川県 児童区分不明 190名
・2026/5/20 石川県 児童区分不明 120名
●実施報告
・2025/5/07 静岡県 中学校 東大寺コースF/W 56名
・2025/5/12 東京都 中学校 オンライン講義 105名
・2025/5/13 奈良県 高等学校 講義+3コースF/W 47名
[2] はばたけ ルリセンチ No.67

[3]当社代表取締役によるコラム
ゴールデンウィークに、イベント学会のメンバーとして大阪・夢洲で開催中の「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」に参加してまいりました。
というのも、イベント学会がテーマウィークスタジオを一日借り切り、前回の万博「愛・地球博」(2005年開催)に関連するさまざまなイベントを行ったからです。
当日行われた主なセッションは、以下の三つでした。
-------------------------
1.「地球市民」が実現する持続可能な社会の提言 ― 世界自然遺産5地域会議
2.「地球市民」が実現する持続可能な社会の提言 ― いのちをつなぐ水と流域
3.「地球市民」が実現する持続可能な社会の提言 ― 関西・歴史文化首都パワー発信プロジェクト
-------------------------
このなかで特に印象深かったのが「世界自然遺産5地域会議」でした。
現在、日本の世界遺産は26件ありますが、そのうち21件は文化遺産または複合遺産で、純粋な「世界自然遺産」はわずか5件しかありません。
世界自然遺産は、そこに存在する自然そのものが貴重であると同時に、地球環境のモニターとしての役割も果たしています。つまり、人類が地球環境と持続可能な開発の両立を意識するための社会的装置でもあるのです。
そのため、オーバーツーリズムによって自然が破壊されることのないよう、地域住民には細心の注意が求められます。
今回は、国内の世界自然遺産地域の関係者が一堂に会し、それぞれの取り組みや課題について語り合う機会となりました。
まず発表を行ったのは、イリオモテヤマネコで知られる「西表島」と、流氷で有名な「知床半島」です。両地域は世界遺産登録前から観光地としても知られており、登録後はさらに多くの観光客が訪れるようになりました。そのため、オーバーツーリズム対策を念頭に置いた取り組みを進めている地域といえるでしょう。
ところで、皆さんは知床で3年前(2022年)に起きた観光遊覧船「KAZU I」の沈没事故を覚えていらっしゃるでしょうか。乗員・乗客合わせて26名が死亡・行方不明となる大惨事でした。この痛ましい出来事は、旅客船事業への国の監督強化、そして海上保安庁の救助体制強化のきっかけとなりました。
その知床で、観光船とは正反対の活動を続けているのが「知床財団」です。ヒグマ、エゾシカ、オジロワシといった野生生物の生態を観察し、人間の活動が自然環境に過度に影響を与えないように、必要に応じて介入も行う組織です。知床財団には現在約50名のスタッフが所属し、世界自然遺産である知床の大自然を「知り・守り・伝える」ことを目的に、知床自然センター、羅臼ビジターセンター、知床五湖フィールドハウス、ルサフィールドハウスを拠点として活動しています。
奈良で言えば、奈良市観光協会・奈良公園室・奈良の鹿愛護会の三つの役割を一手に担っているような団体といえるでしょう。
この財団の原点を伝える印象的なエピソードがあります。
コードネーム97B-5、またの名はソーセージ。初めて出会ったのは1997年秋、彼女は母親からはなれ独立したばかりだった。翌年の夏、彼女はたくさんの車が行きかう国立公園入口近くに姿を現すようになった。その後すぐ、とんでもない知らせが飛び込んできた。観光客が彼女にソーセージを投げ与えていたというのだ。それからの彼女は同じクマとは思えないほどすっかり変わってしまった。人や車は警戒する対象から、食べ物を連想させる対象に変わり、彼女はしつこく道路沿いに姿を見せるようになった。そのたびに見物の車列ができ、彼女はますます人に慣れていった。
我々はこれがとても危険な兆候だと感じていた。かつて北米の国立公園では、餌付けられたクマが悲惨な人身事故を起こしてきた歴史があることを知っていたからだ。我々は彼女を必死に追い払い続け、厳しくお仕置きした。人に近づくなと学習させようとしたのだ。しかし、彼女はのんびりと出歩き続けた。
翌春、ついに彼女は市街地にまで入りこむようになった。呑気に歩き回るばかりだが、人にばったり出会ったら何が起こるかわからない。そしてある朝、彼女は小学校のそばでシカの死体を食べはじめた。もはや決断の時だった。子供たちの通学が始まる前にすべてを終わらせなければならない。私は近づきながら弾丸を装填した。スコープの中の彼女は、一瞬、あっ、というような表情を見せた。そして、叩きつける激しい発射音。ライフル弾の恐ろしい力。彼女はもうほとんど動くことができなかった。瞳の輝きはみるみるうちに失われていった。
彼女は知床の森に生まれ、またその土に戻って行くはずだった。それは、たった1本のソーセージで狂いはじめた。何気ない気持ちの餌やりだったかもしれない。けれどもそれが多くの人を危険に陥れ、失われなくてもよかった命を奪うことになることを、よく考えてほしい。
-------------------------
出典『知床財団公式サイト』:
https://www.shiretoko.or.jp/activity/higuma/
-------------------------
知床の被害者は「ヒグマ」でしたが、奈良では「鹿」が観光客に噛みついたり突いたりする事故が年々増えています。
鹿愛護会をはじめとする関係団体は、鹿せんべい以外の餌を与えないよう、強い警鐘を鳴らしています。
ただ、ヒグマが相手となれば、その影響は即座に「人命」に直結します。だからこそ、知床ではより厳格な管理と対処が求められています。
持続可能な社会と観光という観点において、奈良と知床が抱える課題はよく似ています。
しかし、知床のほうが問題の輪郭がより明確に、そして深刻に感じられます。
知床では観光客の多くが車で訪れますが、そこはあくまで野生の動物が生きる「自然」であり、管理されたテーマパークではありません。
だからこそ、動物の生息域と人間の生活圏を厳密に分け、クマやシカが市街地に侵入しないよう、何キロにもわたって電気柵が設置されています。
一方、現在の奈良公園には連日多くの観光客が訪れています。
しかし、私たちは知床財団のように、明確な方針を持って野生動物と向き合っているでしょうか。
自然と人との共生、そのあり方を改めて考えさせられたシンポジウムでした。
[4]お知らせ
●学び旅学級新聞の感想を募集しています!
コラムや当社の活動について、皆様のお声をお聞かせください。
メッセージは、下記メールアドレスにて受け付けております。
皆様のご応募、お待ちしております。
【応募先】manabi-jimukyoku@kirsite.com
●学び旅学級新聞へ掲載する記事募集中!
原稿・写真と共にメールにてお知らせください。無料で記事として掲載し、配信いたします。
配信時期についてもお問合せください。
【連絡先】manabi-jimukyoku@kirsite.com
----------------------------------------
配信:株式会社学びの旅
TEL:0742-20-7807 平日9:00~18:00(年末年始を除く)
住所:〒630-8305 奈良県奈良市東紀寺町2-10-1
Web:http://nara-manabitabi.com/
代表取締役 川井徳子
株式会社学びの旅 代表取締役。同社の前身である奈良新しい学び旅推進協議会の立ち上げに尽力し、2020年~2025年まで実行委員長を務める。奈良を舞台にした探究型学習プログラム「奈良SDGs学び旅」を企画・開発し、商品化。教育と地域をつなぐ新しい学びの仕組みを創出した。