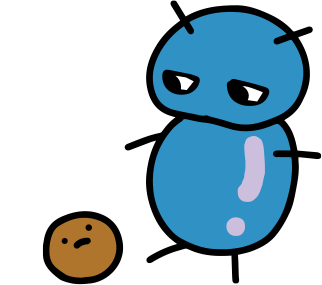
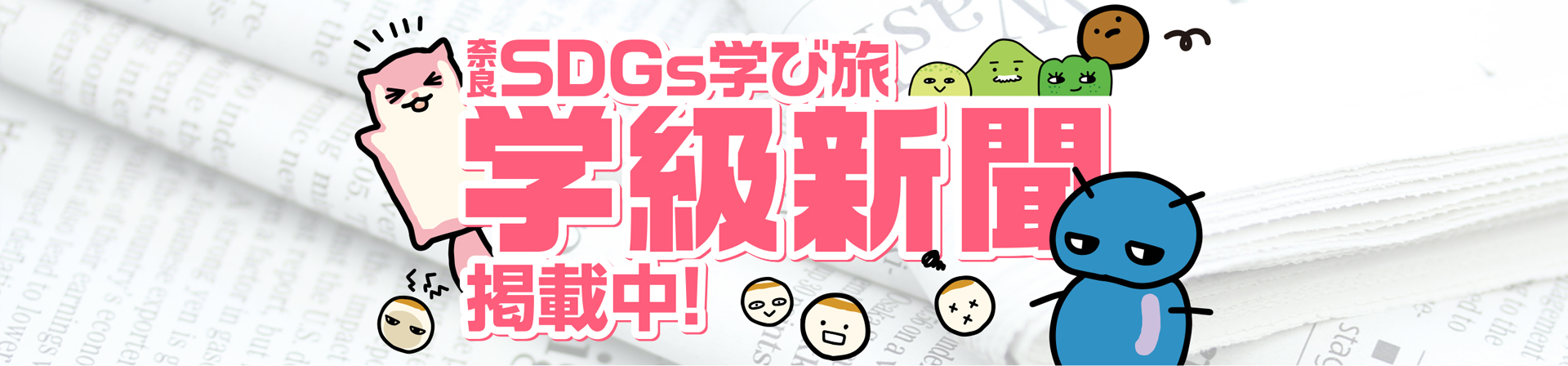

【第62号 2025/2/18 発行】
----------------------------------------
[1] 奈良SDGs学び旅 問合せ報告/実施報告
[2] はばたけ ルリセンチ No. 61
[3] 実行委員長コラム
[4] お知らせ
----------------------------------------
[1]奈良SDGs学び旅 問合せ報告/実施報告
●問合せ報告
・2027/1/19 広島県 中学校 200人
・2026年度 群馬県 不明 120人
●実施報告
・2025/2/10 三重県 中高一貫 3コース分散F/W 101人
・2025/2/14 大阪府 中学校 リアル講義+3コース分散F/W 180人
[2] はばたけ ルリセンチ No.61

[3]実行委員長コラム
皆さんこんにちは
先週、奈良テレビに出演し、奈良SDGs学び旅が2024年度「全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞」を受賞した件について報告しました。
今後、様々なチャンネルを通じて発表していきたいと思います。このような栄えある賞を受賞できるまで「奈良SDGs学び旅」がしっかりと成長できた根っこには、奈良教育大学の存在があります。
ここまで来るのには、教授陣の長くて地道な研究の積み重ねがありました。
中でもESD・SDGsセンター長の中澤先生の取組みはとてもユニークでした。
他の地域や学校のSDGs 学習プログラムは、主に教育×環境問題でできています。
しかし、奈良教育大学は、世界でも珍しい教育×歴史×文化から学ぶプログラムを開発しているのです。
今回はそのユニークさについて解説していきたいと思います。
最初に奈良教育大学がESDに出会ったのは2007年です。ユネスコ本部からニーデルマイヤー博士が来日し、大学でESDについて講演したのです。その時、教授陣は学習内容を変え、子供達に「競争原理」を教えるのではなく、「協働・共創」が可能な人材を育成することが必要なのだと気づいたのでした。
まだ、SDGsという単語も生まれていない時です。
やがて、国際社会の一部に人類社会の「持続可能性」について疑いを持つ人々が、少しずつ増えてきました。ユネスコでも、世界自然遺産として保護される地域の、環境破壊が問題となりつつありました。
その後、国連ではMDGsの成功を踏まえ、2015年~2030年までSDGsに取り組むことが決定され、国連事務総長アントニオ・グレーデス氏は次のように言いました。
"We are in a battle for our lives. But it is a battle we can win."
「これは人類の生存をかけた戦いだ。しかし、この戦いは勝つことができる。」
さらに、ユネスコでも、持続可能な開発を加速するために教育・学習の全ての段階・分野で行動を起こし強化することを目標に、GAP:グローバル・アクション・プログラムが決められました。
「教授法と学習環境」については、双方向性を大切にし、プロジェクトベースで行うこと、学習者中心の教授法としてESDへの機関包括型アプローチを通じて学習環境のすべての側面について変革し、学習者が、学んだことから生き、生きるとはどういうことかを学ぶことができるようにする、と定義されました。
「教育内容」については、気候変動をはじめとするSDGsの17の目標として掲げられた持続可能性に関する課題を、あらゆる種類の学習に盛り込むことが要求されています。
「学習の成果」については、人々が現在と将来の世代のために責任を持ち、社会の変革に向けて積極的に貢献できるような力を養えること、が目標とされています。
それを通じて私達は「社会の変革」を促すことができるのです。
何よりも重要なことは、これは若者たちの問題ではありません。
今を生きる我々、大人が行動を変えない限り達成できないことでもあるのです。
大人こそESDを学ばなければなりません。
現在、世界ではSDGsの「誰一人取り残さない」というキーワードが「One Health=人間、動物、植物、生態系の健康のバランスを持続的に保ち最適化することを目的とした、統合的かつ統一的なアプローチ」に転換されつつあります。
まさに、聖武天皇の大仏造立の詔「乾坤相泰 動植咸栄(けんこんあいやすらかに どうしょくことごとくさかえん)」という言葉が1,300年後の現代にクローズアップされたのです。
地球(天と地)の環境が穏やかで、動物、植物生きとし生けるものすべてが栄えることを祈る、このことこそが大切ではないでしょうか。
レヴィストロースという文化人類学者は、世界の神話を研究していましたが、日本の神話と歴史についても研究していました。
今から50年前、遠くヨーロッパから、次のようなことばで日本文明に大きな期待をかけています。
「人類はこの地球に仮の資格で存在し続けている。『修復不可能な損傷を引き起こすいかなる権利も人類に与えてはいない』ということを日本文明が今も確信しているならば、私の著作の行きついた将来世代の未来への暗い見通しが唯一のモノでなくなるだろう、と。微かではあれ、その可能性を持つことができる 。」
引用元:クロード・レヴィ=ストロース「21世紀のための人類学」『レヴィ=ストロース講義―21世紀のための人類学』岩波書店、2001年
私たち日本人は、50年前にはその意味を理解できませんでした。
しかし、ようやく彼の発言を理解することができるようになった、と私は感じています。子供達だけでなく、大人も含め多くの人々に地球の未来について適切なビジョンを与える必要があるのだと思います。
私たちは、日本の神話・古代社会からのメッセージを現代に伝えていくことの大切なミッションを、担っているのです。
皆さん、頑張って前に進んでいきましょう。
[4]お知らせ
●学び旅学級新聞の感想を募集しています!
実行委員長のコラムや学び旅事務局の活動について、皆様のお声をお聞かせください。
メッセージは、下記メールアドレスにて受け付けております。
皆様のご応募、お待ちしております。
【応募先】manabi-jimukyoku@kirsite.com
●学び旅学級新聞へ掲載する記事募集中!
協議会委員へ告知・共有希望の事柄がありましたら、原稿・写真と共に事務局までお知らせください。
無料で記事として掲載し、配信いたします。
配信時期についてもお問合せください。
【連絡先】manabi-jimukyoku@kirsite.com
----------------------------------------
配信:奈良新しい学び旅推進協議会・事務局
(公益社団法人ソーシャル・サイエンス・ラボ内)
TEL:0742-20-7807 平日9:00~18:00(年末年始を除く)
住所:〒630-8305 奈良県奈良市東紀寺町2-10-1
Web:http://nara-manabitabi.com/